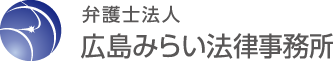昨年、令和6年4月からNHKの朝の連続テレビ小説で「虎に翼」というドラマが放送されていました。ドラマの主人公「佐田寅子」が、男性しか受験資格がなかった高等文官試験司法科(現在の司法試験)に、女性も受験できる様に制度が変更された後に合格し、女性初の裁判官になった人物として描かれました。
この主人公の佐田寅子のモデルが、実際に女性初の判事である三淵嘉子氏であることは、よく知られた話です。
ドラマの中で、最高裁判所長官の講義をまとめ戦前に出版した著書を、新民法に合わせて改稿作業を佐田寅子が手伝うシーンが出てきます。
実際に、初代の最高裁判所長官であった三淵忠彦氏が執筆して、昭和25年2月に補修版として「日常生活と民法」という書籍が公刊されています。これは、三淵忠彦氏が、法律が法律家のためのものではなく、市民にも広く知ってもらう必要があるとの思いで執筆されたものです。
「虎に翼」の反響の大きさも理由の一つと思いますが、一般財団法人法曹会から「日常生活と民法」の復刊新装版が刊行されたので、手に取ってみました。
家庭裁判所は戦後に作られましたが、その設立目的として、分かりやすく次の様に書かれています。
「民法が改正になって家庭を民主化しようということになった。・・・家庭を民主化し、平和にするためには、どうしても第三者の公平な判断と指導がなければならない。気軽に裁判所に事件を持ち出して、しかも当事者が納得するような情誼にかなった解決でなければならない。そうした目的で家庭事件を特別な手続で処理する裁判所が設けられたのであります。」(25頁)
日々の生活の変化に伴って民法も改正を重ねていますが、「日常生活と民法」には、現代にも通じる話が、随所にある様に感じました。