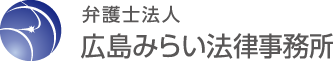今年3月某日JR西日本の木次線(きすきせん)に乗車しました。
島根県出雲市へ出張した帰りに、山陰本線の出雲市駅から広島へ帰る経路に利用しました。
木次線は、1916年10月に宍道と木次間が、簸上(ひのかみ)鉄道により開設され、木次より南は、鉄道省により建設が続きけられて1937年12月に宍道から備後落合までの全通となったものです。営業距離81.9㎞、駅数18駅、単線、非電化です。1953年11月には、米子から木次経由広島までの快速「ちどり」が誕生し、1955年12月には夜行列車の「夜行ちどり」が運転開始されました。しかし、「夜行ちどり」は1980年10月に廃止、「ちどり」は1990年3月に運転区間が備後落合と広島間に短縮され、木次線には定期運行の優等列車が走らなくなり、観光シーズンにトロッコ列車「奥出雲おろち号」が、運行していました。(なお、この列車は2023年11月23日に運転終了しましたが、2024年からは、3月から9月にかけて、土日を中心に観光列車「あまつち」が山陰本線から木次線の出雲横田駅まで乗り入れています。)私は、1970年代半ばに広島駅から「夜行ちどり」を利用して三井野原駅で下車してスキー場に行ったことがありました。
出雲市駅発10時41分の米子行普通列車は、オレンジ色の「キハ47系」の気動車(1970年代後半に製造が開始された)2両編成で乗務員は運転手1人、車内案内は録音音声でした。乗客は、地元の近隣駅へ行かれる人と列車に関心や興味があると思われる方々のようで3割程度の乗車率でした。あいにくの小雨で、少し肌寒い状態でしたが、地元風な人以外は一般の観光客ではないような人が主体で気にもしていないようでした。20分余りで宍道駅に到着。この駅から、木次線の列車に乗り換えましが、ここで、「本日は。雪のため出雲横田から備後落合までは、雪のためバスによる代行運送」と聞かされました。私は、今日中に広島に帰れるのか、ふと不安がよぎりましたが、周りの人は動じることはなかったように見えました。
宍道発備後落合行の列車は、1日に2本(他は途中駅で乗り換え)、そのうちの1本である午前11時17分発の列車は、「キハ120系」の気動車(輸送量の少ないローカル線用)、木次線用に黄色と緑を基調とする塗装された2両編成、乗務員は運転手1人、乗客は20人程度、定刻通り発車。気動車はエンジン音を高めながら山中を走行。発車してもしばらくは雪を見ることはなく、見ることはあっても木々や地面にうっすら色づいているような状態でした。前述のとおりで、出雲横田より先はバスの代行輸送と聞かされていましたが、雪を見ることも少なく、もしかしたらこのままこの車両で進行するのではないかとひそかに期待していました。

出雲横田駅には、定刻通り13時前に到着。駅の周りには雪が残っており、先行きの積雪を予想するに十分でした。代行バスは、すでに待機していました。ここから備後落合駅までの代行バスによる運行が現実となりました。出雲横田駅の駅員は、JR西日本の職員ではなく、委託受けた人が勤務していました。その人の話によると3月までは、バスによる代行輸送は、しばしば行われ、列車の運行時間よりも早く遅れることはないとのことでした。代行バスは、20人乗り程度のJRから委託を受けた会社のマイクロバス、私を含めて10人余が乗り込み、13時10分頃出発しました。運転手は、何度も運行の経験を走行しておられるとのことで、積雪がある個所の道路であっても走行中に危険を感じることはありませんでした。バスは、途中の八川駅、出雲坂根駅、三井野原駅、油木駅の各駅で停車、乗客は降りて写真を写していました。列車であれば、出雲坂根駅から三井野原駅までの間に木次線最大の見せ場といわれる「三段式スイッチバック」を進行できたのですが、出雲坂根駅の付近で、線路の一部を見るだけになりました。次の三井野原では、雪景色となり、冬を感じましたが、スキーができるほど積雪がなく、こじんまりしたモダンな駅舎と線路を見て、昔日の思い出に浸りました。


その後も、代行バスは順調に走行して、備後落合駅に列車の到着予定時刻より早く着きました。この駅からは、芸備線となり気動車1両でワンマンカーの運行、20人程の乗客が乗り、14時40分に三次駅へ出発しました。三次までの各駅では、それまでの駅の乗降客よりも少し増えたようでしたが、座席は満席までにはなりません。
三次駅には、定刻16時に到着、16時5分発の快速列車(気動車2両)に乗車、広島駅に近づくに連れ乗降客は増加、定刻の17時30分到着しました。
出雲市駅を出発して約7時間の旅でした。