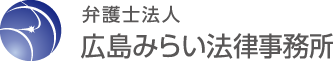1 民法等の改正について
平成30年7月6日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法
2 配偶者の居住権について
今回の改正法で、
この2つの権利には、概ね、以下のような特徴があります。
3 配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、残された配偶者が
被相続人の配偶者(夫又は妻)が、被相続人の所有する居住建物に、相続開始の時に無償で居住していた場合に、
この権利に基づいて居住できる期間は、
①その居住建物が遺産分割の対象となる場合:
②①以外の場合:
⇒例えば、被相続人(亡くなった人)が遺言を残しておらず、
4 配偶者居住権
配偶者居住権は、相続開始後、期間の定めがない限り、
配偶者居住権は、被相続人の配偶者(夫又は妻)が、
また、上記以外にも、
5 適用開始時期
この配偶者の居住に関する2つの権利は、
6 弁護士にご相談を
配偶者の居住権に関する今回の改正は、